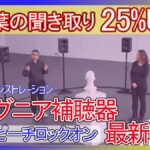Last Updated on 2025年8月25日 by 補聴器専門店ミラックス
音の強さを表す単位「dB(デシベル)」とは?
「デシベル(dB)」という単位、一度は耳にしたことがあると思います。これは「音の強さ」=「大きさ」(音圧)を表すために使われる単位です。
ただし、このdBにはいくつかの“種類”があるのをご存じでしょうか?
たとえば、「dB SPL」「dB HL」「dB SL」といったように、後ろにアルファベットが付いて区別されているのです。
その意味を理解するには、まず「音とは何か」「なぜデシベルという単位が使われるのか」から見ていきましょう。
音は空気の振動、単位は「パスカル(Pa)」
音は空気の振動です。そして振動は圧力の高い部分と低い部分を生みます。この圧力の変化量が音の強さで、単位にはPa(パスカル)が使われています。
このPaは圧力を表す単位なのでいろいろなところで目にしていると思います。一番身近なのが、ヘクトパスカルでしょうか。これは主に気圧を表す単位として広く知られていますが、ヘクトパスカルはパスカルの100倍を表す単位で、1hPa=100Paとなります。

人の耳が感じる音圧の範囲
では、私たちが聞き取れる音の圧力(音圧)はどれくらいでしょうか?
- 最も小さい音:0.00002Pa(20μPa)
- 非常に大きな音(例:ジェット機の近く):20Pa
この0.00002Paから20Paという幅、数字で見るととても扱いにくいですよね。
小さすぎて「0」が並ぶし、大きい方も感覚的にピンと来ません。
しかも、この「20μPa」(マイクロパスカル)は、気圧(およそ1000hPa)と比べると、なんと100億分の2という超微小な圧力差なのです。ちなみにマイクロは100万分の1です。
だからこそ生まれた「dB(デシベル)」という単位
このように極端に小さい音圧を扱いやすく、しかも人の“感覚”に近い形で表すために考案されたのがデシベル(dB)という単位です。
これは、音圧の対数的な比率を使って数値化したものです。
ようやくデシベルが登場しました。
計算式は省きますが、0.00002Pa~20PaをdBに換算すると、0dB~120dBとなります。
ずいぶん扱いやすくなりましたね。0dB=20μPaです。
- 0.00002Pa(最小音圧)=0dB SPL
- 20Pa(非常に大きな音)=約120dB SPL
このように、人の聴覚に合ったスケールで音を表現できるようになったのです。
dBの3つの基準:「SPL」「HL」「SL」の違い
さて、ようやく本題ですが、このdBには以下のような3つの基準値があります。
3つのデシベル
- 音圧レベル<dBSPL>(Sound Pressure Level)
- 聴力レベル<dBHL>(Hearing Level)
- 感覚レベル<dBSL>(Sensation Level)
それぞれ解説していきます。
音圧レベル:<dBSPL>(Sound Pressure Level)
0dBSPLは音圧を人の感覚に合わせて使いやすくした単位で、物理的な測定に使用されています。
- 騒音計
- 補聴器の出力測定
- 音響機器の評価
といった「機械的な音の測定」では、このSPLが使われます。
20μPa=0dBSPL
聴力レベル:<dBHL>(Hearing Level)
0dBHLは健康診断などの聴力測定に使用されます。
こちらは人の聴力の平均値を基準とした単位です。
健聴者がやっと聞こえるレベルを「0dB HL」と定め、それと比べてどれくらい聴力が落ちているかを示します。
- 健康診断の聴力検査
- オージオメーター(聴力測定器)
など、「人の聞こえの測定」ではこのHLが使われます。
感覚レベル:<dBSL>(Sensation Level)
dB SLは、その人自身が聞こえる最小音(しきい値)を0dBとして、どれくらい音を大きくしたかを示す単位です。
個人差を考慮した測定に使われ、聴覚実験や音の聞こえ方の評価などで活用されます。
0dBSLはHLが平均値なのに対して、被験者自身が聞くことのできる最小音量となります。主に実験などで使用されます。

補聴器に関係するのはどの単位?
補聴器の調整では、SPL(音圧レベル)とHL(聴力レベル)の両方が使われます。
| 使用場面 | 単位 | 説明 |
| 補聴器の出力や特性を測定 | dB SPL | 音の物理的な強さを測定する |
| 難聴の程度や聞こえの評価 | dB HL | 聴力と比較してどれくらい補正が必要かを見る |
補聴器からの出力音を測定する特性測定はSPL、難聴の程度を測定する時や、補聴効果を測定する場合などはHLを使用します。
つまり、機械の測定はSPLで、人の聞こえの測定はHL、という風にそれぞれ使い分けているということです。
補聴器の聴力測定で使用するHLは、0dBHLが健聴なので、25dBHLから軽度難聴、40dBHLから中等度難聴と、数字が大きくなるにつれて聞こえが悪くなっていきます。ちなみに健康診断などで測定するのは1000Hzを30dBの音圧で、4000Hzを40dBの音圧で測定し、難聴の度合いを大まかに把握します。
聴力レベルがマイナスもあり得る
前述したとおり、聴力レベルの0dBは健聴者の聞こえを基準にしているので、子供の場合、-10dBなんてこともあり得ます。
悲しいことに、20代をピークに聴力は自然と低下していくものなので0dBよりも悪くなっていることが普通です。
ちなみに加齢性の難聴は高音域から低下していき低域に広がっていきます。若いうちからヘッドホンやイヤホンで大音量の音楽などを聴いていると将来難聴になるリスクが高くなるので注意が必要です。
少し高いけどノイキャン付きのイヤホンがおすすめです。
まとめ
音の強さを表す「dB」には、以下のような意味があります
- dB SPL:音の物理的な強さ(騒音計や補聴器の出力測定に使用)
- dB HL:平均的な人の聴力と比較(聴力検査や補聴器のフィッティングに使用)
- dB SL:個人の聞こえるレベルを基準(聴覚実験などに使用)