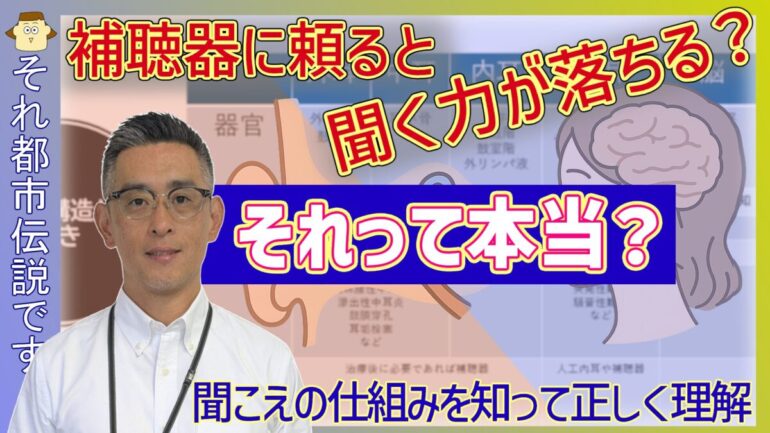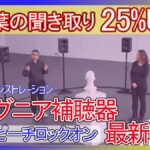補聴器は、低下している聴力を補うためのアイテムです。あくまでも補助アイテムであって「聞く」ことを身体機能以上に拡張するわけではありません。
補助の目的は機能の回復や補完なのに対し、拡張は機能の向上や超越です。
簡単に言えば、補助とは「できるようにすること」「元に戻すこと」であり、拡張とは「すごくなること」「新しい力を追加すること」と言えます。
もっとも最近のデジタル補聴器は、AI搭載などで身体機能の拡張の側面も出てきているので、すべてが当てはまるわけではなくなってきていますが、それでも基本的に補聴器は聞こえにくさを感じている人が使用する補助アイテムです。
実際に、健聴者が補聴器を装用して、身体機能以上の聞こえを獲得しているなんて話は聞いたことがありません。
加齢性難聴に代表される感音難聴は、聴力が低下している周波数帯と、ほとんど問題の無い周波数帯が混在している場合が多いです。
補聴器は低下している周波数帯のみを増幅して聞こえを改善します。
聴覚の働きは、脳に電気信号として送られたものしか認識、処理できません。
そのため、補聴器は、聴覚情報処理の観点からもなるべく装用しておいた方が良い。
補聴器に慣れると、外した時に聞こえにくさを今まで以上に感じることがあります。これは本来の聞こえ方を認識しているので、聞く力が衰えているわけではありません。実際に聴力測定を行っても聴力に変化は見られないのが通常です。
補聴器に頼るのが耳にとって良くない、聞く力を衰えさせてしまう、といったことはありません。むしろ、聞こえているべき音が聞こえていないことの方が問題です。
繰り返しですが、脳は送られてきた電気信号を処理するので、そもそも送られてこない場合は、その情報自体認識できないので、聞く力も何も働きません。
聞こえの場合、問題をわかりにくくしているのが、音声の音量が一定ではないことと、周りの環境音が変化することです。さらにそこに話者との距離と向きが加わり、問題を複雑化させています。
これはつまり、「聞こえる時もあれば、聞こえないときもある」「聞こえているけどたまに聞き取れない」といった状況があるため、「それでも聞こえていることの方が多い気がする」「だから、補聴器は必要ないかも」、といった結論になりがちだということです。
補聴器はできるだけ健聴者と同じように聞こえることを目指しますが、残念ながら様々な要因で同じにすることは難しいです。特に語音明瞭度(言葉の聞き取りの能力)が低い場合は様々な工夫が必要になってきます。
そのため、同じような聴力レベルで同じクラスの補聴器を選択したとしても、補聴器に対する聞こえの満足度は人によって異なります。
これは実耳測定で設定、調整しても同じです。※ただし、実耳測定をしないとその差分はさらにわかりにくく、難しい調整となります。
補聴器装用は早めがおすすめです。
言葉の聞き取りの能力(語音明瞭度)が低下する前に早期の装用をおすすめします。